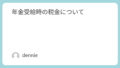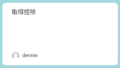取得税を引いた公的年金が実際にいくら貰えるかを計算します。
ただしこの計算は正確な金額ではなくあくまでも予想の金額になります。
流れ
以下の流れで計算します。
- 年間の公的年金収入額を予想する
- 公的年金控除額を確認する
- 公的年金雑取得を求める
- 総所得額を計算する
- 課税取得額を計算する
- 取得税を計算する
取得税の計算
年間の公的年金収入額を予想する
自分が貰える公的年金収入額を予測します。
公的年金
受領できる公的年金(厚生年金含む)の金額を以下のWEBサイトからシュミレーションします。
・厚生労働省のシュミレーター
https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/main.html
個人型確定拠出年金
idecoのような個人型確定拠出年金も公的年金と同じ扱いになります。idecoをやっている場合は、以下のWEBサイトから受領額をシュミレーションします。
・金融庁のシュミレーター
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/tsumitate-simulator/
公的年金収入額の計算
公的年金(厚生年金含む)の金額と個人型確定拠出年金(idecoをやってる場合)を合算し、公的年金収入額を計算します。
公的年金控除額を確認する
下記の表より公的年金収入額に当てはまる公的年金控除額を確認します。なお、下記は公的年金を65歳から受け取る場合の表になります。
控除額は例えば、シュミレータで計算された公的年金収入額が200万だった場合、110万円となります。
| 公的年金収入額 | 公的年金等控除額 |
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円〜330万円未満 | 収入額-110万円 |
| 330万円〜410万円未満 | 収入額×0.75-27万5,000円 |
| 410万円〜770万円未満 | 収入額×0.85-68万5,000円 |
| 770万円〜1,000万円未満 | 収入額×0.95-145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入額-195万5,000円 |
公的年金雑取得を求める
公的年金雑取得は以下の式により計算します。
公的年金雑取得 = 公的年金収入額 - 公的年金控除額例えば、公的年金収入額が300万円だった場合、以下のようになります。
300万円 (公的年金収入額) – 110万円 (公的年金控除額) = 190万 (公的年金雑取得)
総所得額を計算する
公的年金は雑取得扱いとなります。雑取得は総合課税所得になるので、その他の取得と合算して税金を計算します。
例えば、給与取得がある、個人年金保険の取得がある場合、公的年金雑取得に合算する必要があります。
総所得額 = 公的年金雑取得 + その他の取得公的年金のみの場合は、その他の取得は考慮する必要がないので、公的年金雑取得が総所得額になります。
課税取得額を計算する
総所得額から取得控除を差し引いた額が課税取得額となり、これが課税対象額として計算に使用されます。
課税取得額 = 総所得額 - 取得控除取得控除については以下を参照して下さい。
基礎控除、社会保険料控除が控除対象となります。65歳以上でも生命保険料を支払う場合、支払った生命保険料も控除対象になります。医療費控除は年間10万円もしくは取得の5%の金額を医療費として支払う場合に対象となります。場合によって対象となる控除が変わるので確認しましょう。
今回は、基礎控除、社会保険料控除が控除対象の場合を想定します。
総所得額が190万円だった場合、以下のようになります。
190万円 (総所得額) – 58万円(基礎控除) – XX万円 (社会保険料控除) = XX万円